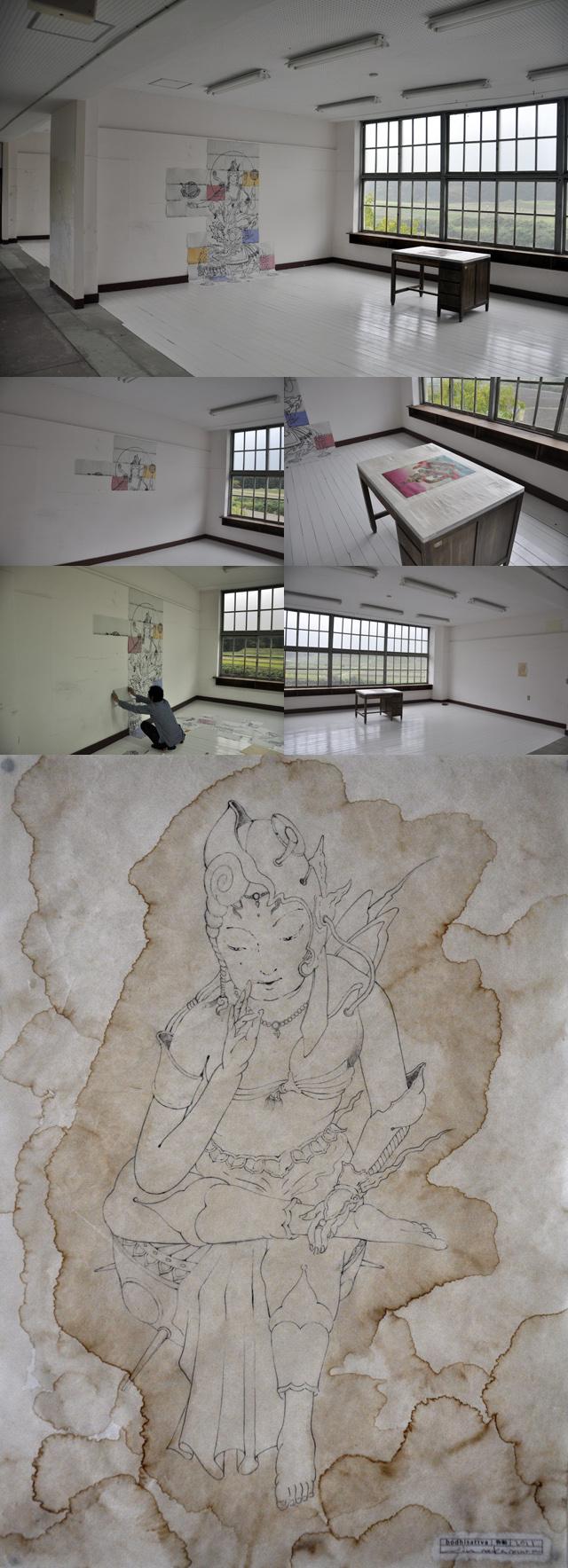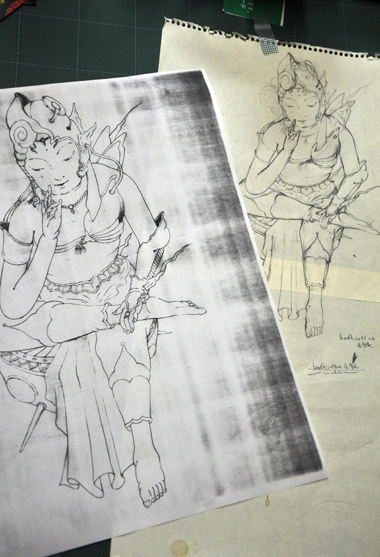西国紀行_6
- By jin
- In etc.
- With No Comments
- Tagged with 俳句 旅
- On 3 11月 | '2011
 ながらく続けてきました西の旅紀行の締めは京都タワー展望台から大阪・兵庫方面を望むの圖で。ツレのオネエさまのたっての希望(泊まったホテルでタダ券をもらったので、というのが真相)でのぼりました。茜色に暮れようとする西空につい昨日の友人たちとのあわただしいサヨナラを重ね合わせてチト感傷的…いわゆる祭りの後症候群(?)というところでしょうか。とはいいつつもやはり旅はよいものオツなもの。そのうち芭蕉翁にならって吟行などやってみたいものです。そういえば最近誘われて始めたまったくお金のかからないオトナの遊び「句会」仲秋の巻の僕の投句などをついでに…。
ながらく続けてきました西の旅紀行の締めは京都タワー展望台から大阪・兵庫方面を望むの圖で。ツレのオネエさまのたっての希望(泊まったホテルでタダ券をもらったので、というのが真相)でのぼりました。茜色に暮れようとする西空につい昨日の友人たちとのあわただしいサヨナラを重ね合わせてチト感傷的…いわゆる祭りの後症候群(?)というところでしょうか。とはいいつつもやはり旅はよいものオツなもの。そのうち芭蕉翁にならって吟行などやってみたいものです。そういえば最近誘われて始めたまったくお金のかからないオトナの遊び「句会」仲秋の巻の僕の投句などをついでに…。
「秋風に 消えようとする 飛行雲」
「十六夜の 琥珀に進化 とどめけり」
「吾も亦 紅なり君の ほほ染めて」
そんな感じカナ。