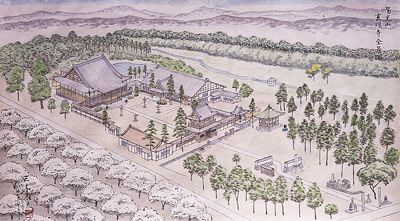初冬の句
- By jin
- In culture
- With No Comments
- Tagged with 俳句
- On 17 12月 | '2011
初冬の句会。ナカムラの投句は以下三句です。
「さむ風に てぶくろの中 にぎるゆび」
「漆葉の 朽ちて深紅は 過去世こと」
「冬蠅の 傍若無人に 振る舞える」
いきなり解説を添えるのは野暮というもの。ネタばらしは後日1週間後くらいに。覚えていたら…
女性5名+男性2名のネット句会なのです。住まうところも遠く離れ、なので季節の感じ方もさまざま。詠み人の暮らす風景など想像をしながらメールで送られてくる17文字を読み解くのは楽しくもあり、ちょっとだけスリルもありますね。「想像する」というと聞こえはいいですが時として「妄想する」とも言えなくもない。もしかして本人にはまったくそんな気はなく詠んだ句にも妙な艶っぽさを感じてみたりして。半分くらいの人はお顔も知らないのに当句会の主宰のご縁でつながってるわけで、そんな方々にたった17文字とはいえココロの内を吐露する言霊を送るわけですからちょっと不思議な気分です。「俳句」という言語でつながる日本的でマニアアックで最小単位のSNSってところでしょうか。