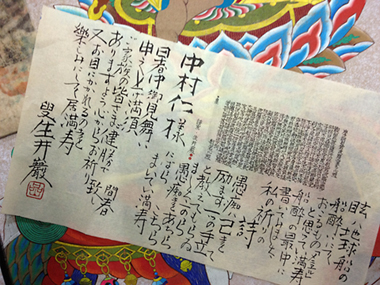中秋の句
- By jin
- In log
- With No Comments
- Tagged with 俳句
- On 28 10月 | '2012
地に惹かれ落つ若栗の成行きに
目の前で青毬の栗が落ちたんですよ。とはいってもアイザック・ニュートンさんみたいにそこに科学を感じたわけではなく、ただただ、あーそうだよね~、そうなるよね~…って。落ちることが不吉に思ったわけでもなく、栗が簡単にゲットできてラッキーと思ったわけでもなく、それでイイんじゃね、ってさ。
片鱗をみせてみようか秋の空
秋の大空を埋め尽くすうろこ雲をみてたらなんとなく。全部見せろといわれたらチト困るけど、片鱗くらいならなんだか見せられるような気がしません?
年下の父の遺影や秋彼岸
気がついたら父の享年を越えていた…ということではないのです。彼が他界したのは本人が40代前半なのですでに10年ほど父を越えて生きてることになり、もちろんそのことは承知してました。問題は遺影です。高校野球のお兄さんがいつまでたっても自分より大人びて見える…あんな感じかな。昔のことなんで旬な遺影撮影などしていたわけもなく、亡くなった時よりもさらに若い頃のものだったはず。なのに未だに自分より年下の人には見えない不思議。なんでだろ…。