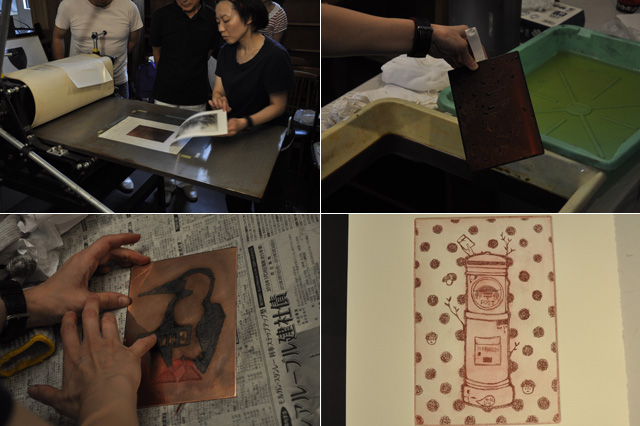hay fever
- By jin
- In etc.
- With No Comments
- On 28 8月 | '2013
本年度秋のアレルゲン許容値を一昨日越えたらしく、夜中に鼻水とくしゃみが止まらなくなり朦朧とした思考のまま合法ドラッグに手をだす。結果症状は治まってはいるものの眠気、思考・集中力の低下といった副作用が著しい。興奮状態とは逆の作用をもたらすので、なんかこう一日ボー…っとした空気感のなかを漂ってる感じで、その愚鈍な感じがすべての外的刺激から解き放たれたようで心地よくさえ思える。それは感覚としては非日常的でちょっと面白いんだけれど、当然薬物がもたらす不自然な感覚なので、以後はマスクなどを使用してできるだけ控えようと思う。